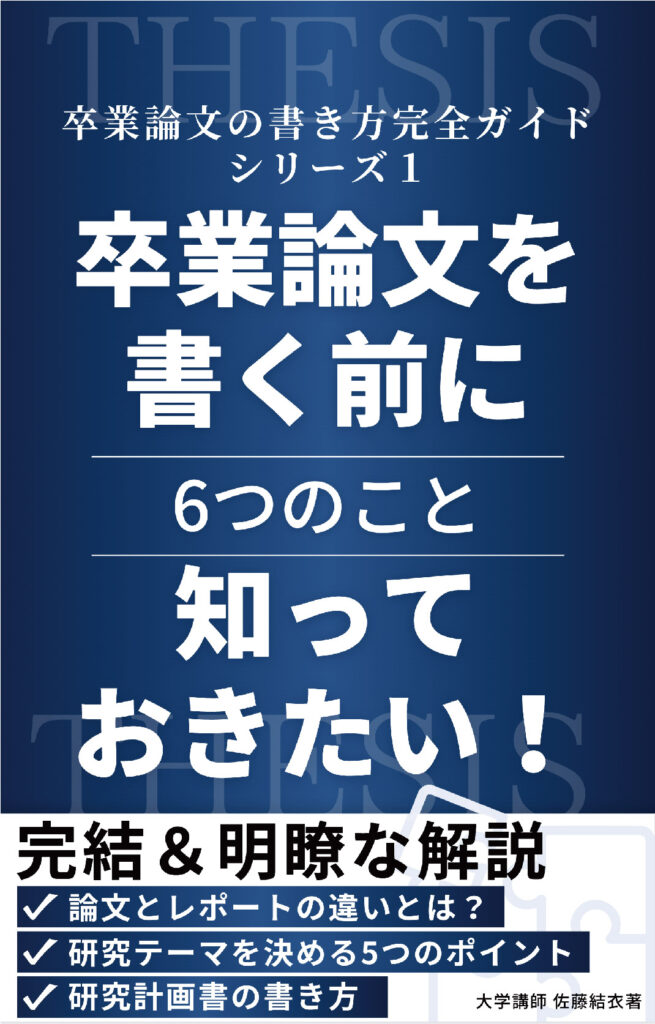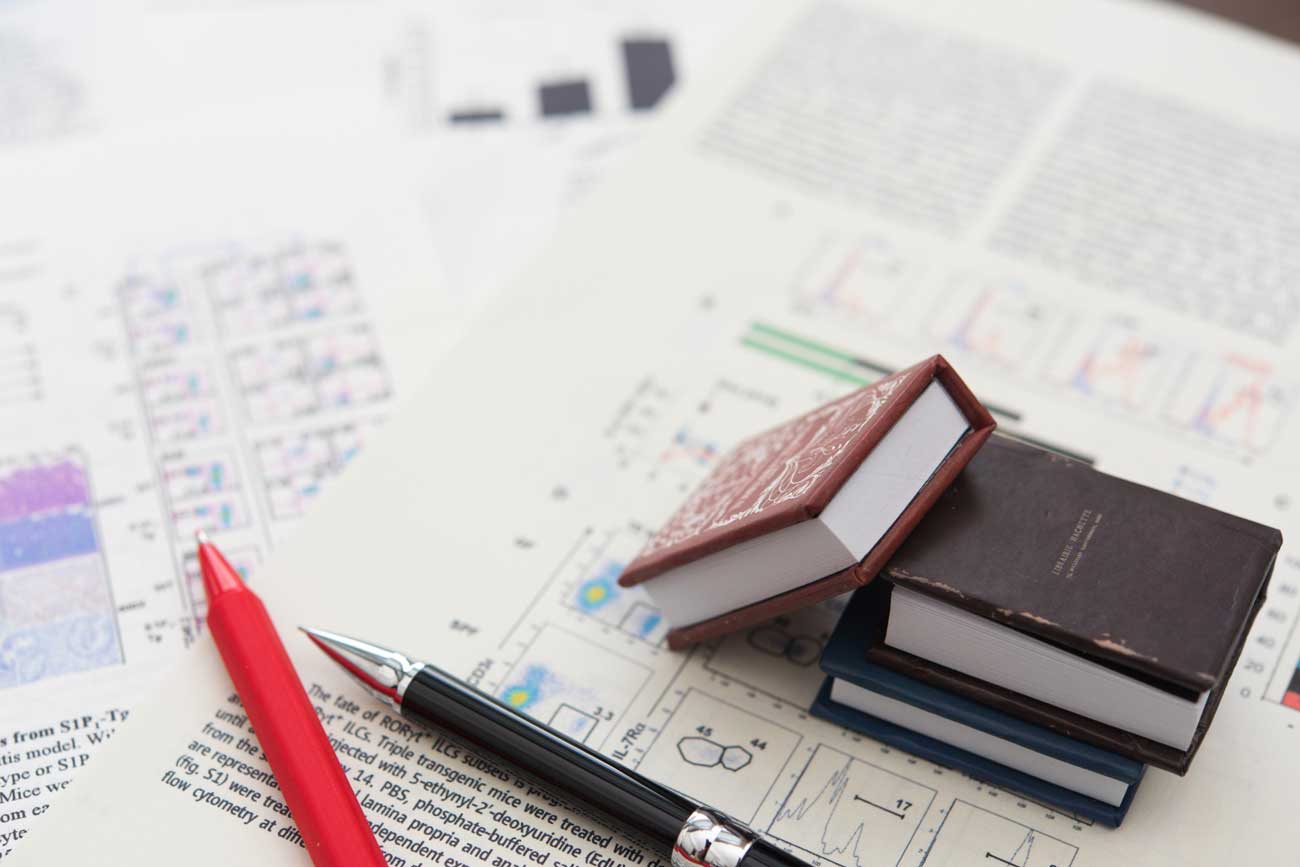卒業論文の書き方完全ガイド販売中!『書き方徹底解説編 目次&例文あり』
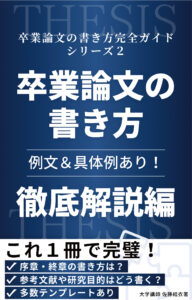
春は卒論のテーマを決める時期、社会が混乱していても当たり前のように卒論提出は迫ってきます。多くの文系学生が抱える悩みそれは「卒論、どんなテーマで書けばいいんだろう?」という問い。この問いが一番難しいんじゃないかと思っている人も多いはず。
明確なテーマを示すことはできませんが、現役の文系大学院生が卒論のテーマを決める際に押さえておくべき5つの点をわかりやすく解説します。
卒論テーマがどうしても決まらない!という方向けに、具体的な3つの方法を紹介した記事も書いています。あわせてご覧ください。
【即実践可能】卒論のテーマが決まらない&思いつかない人におすすめの3つの方法
「卒業論文の書き方全般を0から知りたい!」という方はこちらの記事もご覧ください!
この記事の内容はYouTubeでも解説しています。「聴きながら学べる」コンテンツになっているので、ぜひご視聴ください!
【あわせて読みたい】卒論で疲れた学生におすすめの疲労回復グッズ&サービス7選
【あわせて読みたい】卒論でバキバキになった身体をほぐす!おすすめマッサージグッズ8選
1年間興味関心が持続する卒論テーマを選ぶ
文系学部制の場合多くは4月5月で卒論テーマを決め、6月~夏休み明けに参考文献を読んだり調査したりし、10月以降に本文を執筆、12月1月に提出するという流れかと思います。約1年かけて卒論を書くという事は、裏を返せば1年間興味関心が持続する本当に自分が追求したいテーマを最初に決めるべきだということです。
よくある失敗は当初計画した卒論テーマで進めてみたもののうまくいかなかったり途中で飽きてしまった夏休み明け頃に急に方針を転換するというケースです。これでは密度の高い文献調査や質の高い丁寧な調査、何度も見直しを重ねることはできません。一生に1度しか書かない卒論をより満足いくものにする為に、最初の卒論テーマを決める際に妥協しないようにしましょう。
当事者性の高い「自分にしか書けない」卒論テーマにする
他人にも書ける卒論はわざわざあなたが時間を割いて書く必要はありません。文系の卒論で大切なのは大なり小なり「当事者性」です。当事者性とは「自分も当てはまるもしくは自分の身近な問題を取り扱う」ということ。ボランティアの卒論を書くにしても、普段ボランティアをしている人が書く内容と1度もボランティアしたことがない人とでは読者の共感や熱量が異なってくるのです。
ではどうすれば当事者性の高い卒論が書けるのでしょうか?絶対的な正解はありませんが友達や先生におすすめされた愛着の無いデーまで書くのはやめましょう。これまでの大学生活や家庭環境、アルバイトを振り返り疑問に思ったことや体験して驚いたことなどをテーマとして設定してみましょう。そうすることで世界中でただ1人「あなたにしか書けない卒論」が完成します。
絞りすぎと思うくらい卒論テーマは絞るべき(※広げすぎない!)
文系学部生が卒論を書く際に一番失敗しがちなのは「テーマを広げすぎる」こと。「日本における~」「現代の世界において~」のように括りを広くすることで本当に追求したいテーマがぼやけてしまいます。またテーマを広げすぎると到底個人ではできないデータや資料を相手にすることになってしまいます。
大きなテーマで卒論を書きたい人の気持ちは分かりますが(私も学部時代そうでした)、ここはぐっとこらえて「1つの絞った事例を深く深く追求し、その結果をもとに大きな考察を行う」という姿勢を大切にしましょう。
テーマを絞ることは決して負けではありません。絞った1つの事例を誰よりも深堀することで大きなテーマにも通じるものが見えてくることもあります。現実的なスケジューリングと興味関心を重ねて可能な範囲で卒論テーマは決めましょう。
Google ScholarやCiNiiで先行事例を調べる
卒論テーマ決めで最も重要なのは「先行事例を調べる」ことです。そのときに使えるのがGoogle ScholarやCiNiiなど論文が掲載されたサイトです。
Google Scholarはオンライン上に掲載されている論文を1か所で検索できるようなシステムです。CiNiiは日本で最も使われている論文掲載サイトでGoogle Scholarよりも信頼性が高いといえます。この点について他のサービスも含めてさらに詳しく知りたい方は、下の記事もあわせてご覧ください。
卒業論文の先行研究・参考文献の探し方-現役大学院生がおすすめする7つの方法-
どちらのサイトも無料でダウンロードして読めるものが多くあるので、まずは興味あるキーワードを入力し無料でダウンロードできる論文を読んでみましょう。
そのうえで「これはどうしても読みたい!けど無料でダウンロードできない!」というものは、大学図書館を通して取り寄せてもらったり実際に置いてある図書館に行くなどして読みましょう。手間暇をかけて見つけた優れた自身の興味関心と重なる論文から学べることはとても多いのでめんどくさがらず使ってみましょう!!
卒論の参考文献の書き方・文字数・書き忘れないための方法などについて知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
【あわせて読みたい】卒業論文の先行研究が見つからないときに試したい5つの方法
あえて興味関心とちょっとズレた本や論文を読む
卒論のテーマを決める際、できる限り早い段階でテーマを決めないと方向性が定まらず遅れをとってしまうと焦る人は少なくありません。しかし私はあえて「興味関心とちょっとズレた本や論文を読む」ことを4年の夏休み前まではおすすめします。なぜなら早い段階でテーマや方向性をガチっと絞ってしまうと「あっ」と言わせる視点や新規性に欠けてしまう可能性があるからです。
教授や図書館のおすすめ本を読むのもいいですが、ぜひ卒論のテーマを決める時期こそ普段読まない本に手を伸ばしてみてください。そうすることで、これまで行き詰っていた人はパッと道が開ける感覚を得たり、方向性が決まっていた人も「こういうアプローチもできるな」と新しい方法を見つけられるはずです。
論文の書き方を学ぶのにおすすめの本
論文の書き方をより詳細に解説したおすすめの3冊を紹介します。『社会科学系論文の書き方』は文系の中でも社会科学系の学部に属する人におすすめの1冊です。『論文の書き方改版』は日本を代表する社会学者清水幾太郎が自身の体験をもとに執筆した論文を書くための姿勢やコツを解説した分かりやすい1冊です。『大人のための国語ゼミ』は論文だけに留まらず「国語力」を鍛えるために必読の1冊です。
ここで紹介した以外の卒論執筆解説本を知りたい方はこちらの記事もご覧ください!
最後に-卒論テーマが決まればあとはひたすら前進するのみ-
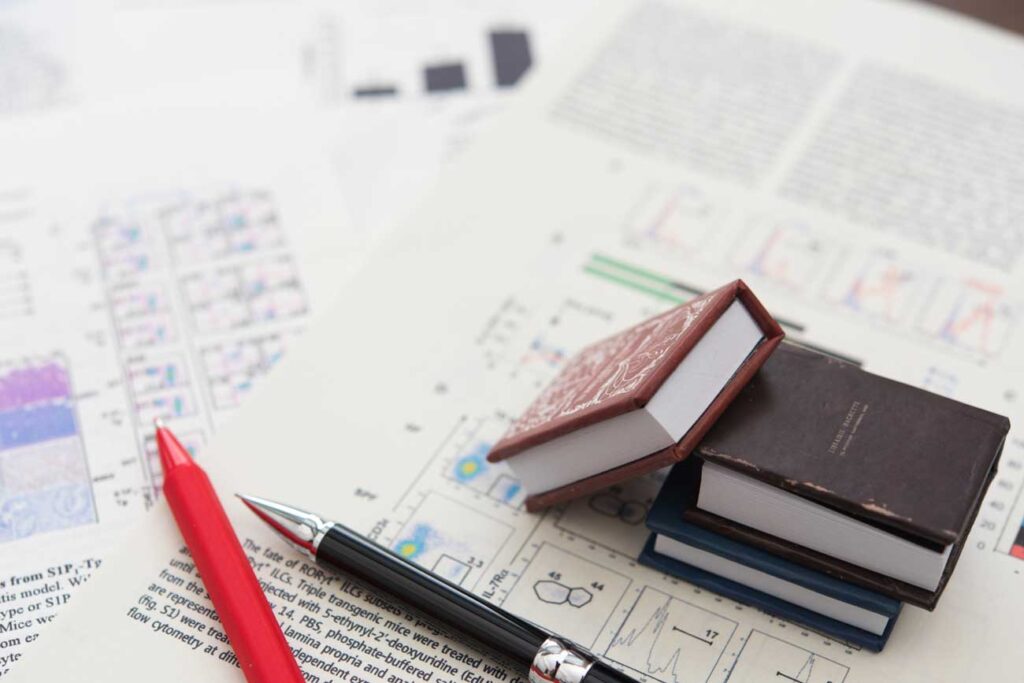
学部生の皆さん、卒論のテーマ決めはとても難しいと思いますが「1年間、興味関心が途切れないくらい調べて見たいこと」をぜひテーマに据えましょう。教授に言われたから、友達が似たようなことをしているからでは途中でやる気は途切れてしまいます。卒論のテーマさえ決まればあとは前進するのみなので、ぜひ自分にしかできない卒論のテーマを設定してみてください。
卒論のテーマを論文に落とし込む際には、研究目的という形で書くことになります。研究目的って何?研究目的の書き方がわからない!という方は、こちらの記事もあわせて読んでみてください。
卒論の「研究目的」の書き方を、わかりやすく解説!-例文・やってはいけないことリストあり-
卒業論文の書き方完全ガイド販売開始!シリーズ1冊目は『卒論を書く前に知っておきたい6つのこと』